「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事や生活に役立つ情報を発信しています!
気がついたら頑張りすぎている…
そんな経験はありませんか?
- 仕事や作業に集中しすぎて、気づけば疲れ果てている。
- 帰宅したらぐったりして動けない。
- 週末は疲労回復で終わってしまい、何もできない。
このような状況が続くと、生活の質が下がってしまいます。

では、どうすれば頑張りすぎを防ぐことができるのでしょうか?
まずは自分の疲れを「見える化」してみませんか?
「頑張りすぎ」〜実際に起きた出来事から
私は就労移行支援を利用し、障がい者雇用で就職しました。
その中でオーバーワークをしてしまい、体調を崩した経験があります。
その日の作業内容
午前中 ➡️ 施設外就労
午後 ⬇️
- Excelでの作業
- 「突然」施設内の清掃を任される
- 再びExcelの作業を再開
- Excelの作業終了後、別の作業で他の方のサポートを担当
- 「過集中しすぎて」疲労がピークに達する
- 関係ない考え事をしてしまい、さらに疲れる
- 作業完了後「フラフラになり」職員に報告して休憩
その日のフィードバック
振り返ってみても、明らかに作業過多でした。
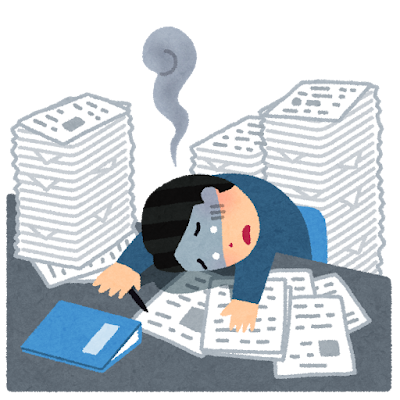
特に施設内清掃に関しては、職員が事前に担当者を決めておらず、
Excel作業中に突然後ろから話しかけられた形でした。
私は「突然の作業変更」が一つなら何とか対応できますが、
二つ以上重なるとパニックになりやすいと実感しました。

また疲労が蓄積していたにも関わらず
「自分は頑張っている」という自覚がありませんでした。
作業中は「ちょっと忙しいくらいかな…」としか思っておらず、
終わって初めて「やりすぎた」と気づいたのです。

次の日、日報を見ると職員から
「作業を振りすぎて申し訳ありません…」というコメントがありました。
この経験から「頑張りすぎないための対策」を考える必要性を強く感じました。
頑張りすぎを防ぐためにできること
1. 疲れたらすぐに報告する
まずは「無理だ」と思った時点で、すぐに周囲に伝えること。
「まだできるかも…」と自分を過信せず、
✅️「疲れたので少し休憩します」
✅️「この作業は難しいので、手伝ってもらえますか?」
と、早めに周囲に伝えることが大切です。
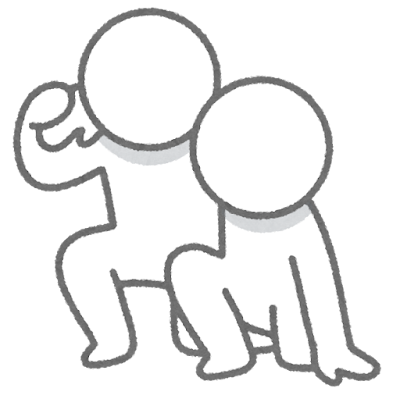
もし「まだできるでしょう」と言われた場合、
その相手とは距離を置くのも一つの方法です。
無理を強いる環境では、自分の健康を守れません。
信頼できる人に助けを求めることが重要です。
2. 自分の疲労度を数値化する
「自分がどれくらい疲れているか」を把握するのは意外と難しいものです。
以前紹介した「疲労カウンター」を活用するのも良い方法です。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください⬇️
3. 休憩を計画的に取る
過集中しやすい人ほど、意識的に休憩を取ることが大切です。
- 「30分〜1時間ごと」に「5〜10分の休憩」を入れる
- 作業の合間に「ストレッチ」や「軽い運動」をする
- 外の空気を吸う、目を閉じるなどしてリフレッシュする
「疲れてから休む」ではなく「疲れる前に休む」を習慣にしましょう。
4. 予定外の作業に備える
突然の作業変更があるとパニックになりやすい方は、
以下のような対策を考えてみてください。
- 「急な作業は対応できません」と事前に伝えておく
- 追加作業があった場合は、優先順位を整理する
- すべてを引き受けず「どれを減らせるか」を職員と相談する
すべてをこなそうとせず、できる範囲で対応する意識が大切です。

5. 「やるべきこと」と「やらなくてもいいこと」を区別する
頑張りすぎてしまう人は「すべてを完璧にこなさなければ」と考えがちです。
しかし「本当にやるべきこと」と「実はそこまで重要ではないこと」を
見極めることが大切です。
- 「絶対に今日やるべき作業」は何か?
- 「余裕があればやる作業」は何か?
このように区別することで、 必要以上に頑張りすぎるのを防げます。
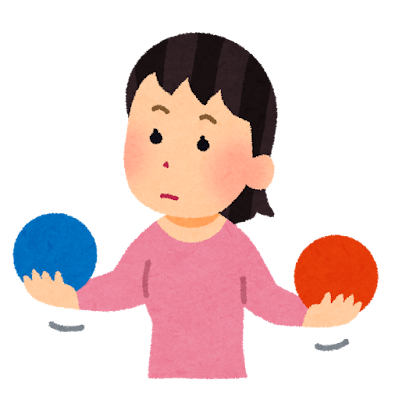
まとめ〜自分を大切にするために
疲れをためすぎないためには「自分の状態を把握すること」が大切です。
もし自分で疲れを認識しにくい場合は、
周囲の人に「自分が疲れていないか」確認してもらうのも有効です。
他人は、あなたの疲れた表情や仕草に気づきやすいものです。
「最近、ちょっと無理してない?」と言われたら、
一度立ち止まって自分の状態を振り返ってみましょう。
疲労でダウンしてしまうことを繰り返さないために、
「頑張りすぎない習慣」を意識してみてください。
あなたにとっての「頑張らない工夫」は何ですか?
ぜひコメントで教えてください!




コメント